100億企業創出シンポジウム
イベントレポート

100億企業への飛躍を実現する「実践知」
M&A・人材・金融の戦略的活用法
2025年10月7日(火)に開催された「100億企業創出シンポジウム」では、講演の後、パネルディスカッションが行われました。登壇者は、前田工繊株式会社(福井県)代表取締役社長 前田尚宏氏、浅野撚糸株式会社(岐阜県)代表取締役社長 浅野雅己氏、株式会社ONDOホールディングス(埼玉県)代表取締役社長兼グループCEO 山崎寿樹氏、株式会社日本政策投資銀行 取締役常務執行役員 増田真男氏です。
司会を務める中小企業庁の赤松氏は、先の冨山和彦氏の基調講演を受け、こう切り出しました。
「冨山さんのお話を早速、経営の現場に落とし込んでいきます。端的に申し上げますと、『デフレ思考から脱却し、人材を確保した企業が勝者となる』ということでした。ご登壇いただいている皆さまは、それを実践されている方々です」
ディスカッションは、100億企業を目指す上で欠かせないM&A、人材確保、そして銀行からの成長資金の確保といった「経営の核心」に迫るテーマを、地方から成長を続ける3社の具体例と共に具体的に掘り下げていきました。
3人の経営者が語る成長ストーリー
前田尚宏氏(前田工繊株式会社)──危機感が生んだM&A戦略

前田工繊株式会社は福井県に本社を置くインフラ資材の製造・販売企業で、従業員1,848人、売上高640億円。そして前田氏が掲げる次の目標は1,000億円です。
「入社した当時、売上の9割が建設資材でした。公共事業向けの資材が主力でしたが、構造改革の影響で公共事業が3割減少。上場を目指すには新たな成長ストーリーが必要でした」
転機となったのは、たまたま成功したM&Aです。
「隣の業界でもあり、リスクも少ないだろうと考え、後継者がいないという港湾や河川で使うオイルフェンスなどを作っている会社をグループに迎え入れました。そこからM&Aの効果を実感し、戦略的に取り組むようになりました」
現在までに17社のM&Aを実施。特に印象的なのがBBSジャパンの事例です。BBSは、ドイツ発祥の世界的に有名な高級アルミホイールメーカーで、レクサスなどの高級車に純正採用されています。
「BBSジャパンの買収当時の売上高は30億円でしたが、現在は250億円超まで引き上げました。4年前から、F1カーの統一ホイールとしても採用されました」
前田氏の成長戦略で「M&A、多角化、海外展開」は欠かせません。
「1つの事業だけでは、市場の上げ下げに対応しきれません。祖業だけやっていても厳しい。とにかく、危機感が大きかったのです。M&Aは新たな血を入れる、文化を入れるという意味でも有効でした」
司会の中小企業庁から前田氏に「社長は政治、経済、国際情勢などマクロが好きですよね?」という問いかけがありました。これは多角経営を進める経営者にとって「潮目の変化を逃さない」「大事な判断を間違えない」ための、極めて重要な視点であるようです。
入社当初の年商、約70億円から640億円へ。地方の中堅企業として、危機感を力に変えた成長の歩みは、多くの経営者に勇気と新たな決意、そして具体的な経営のヒントをもたらしたのではないでしょうか。
浅野雅己氏(浅野撚糸株式会社)──「下請け」からの脱却と100億企業への挑戦
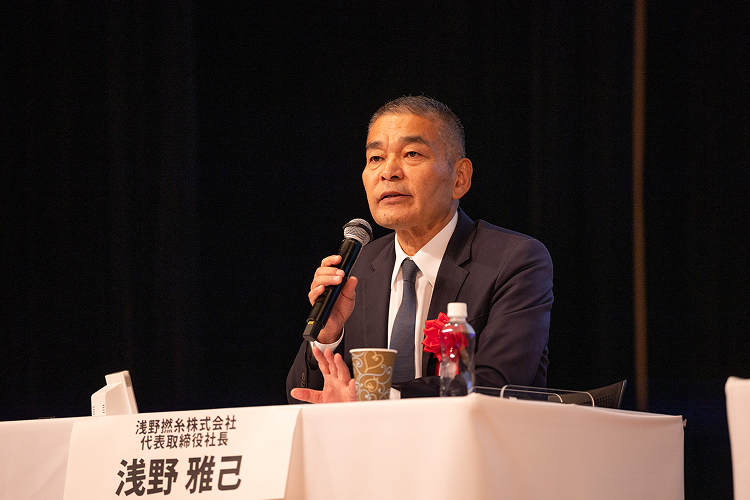
浅野撚糸株式会社は岐阜県に本社を置く製造・販売企業です。紡績の下請けとしてスタートした同社は、現在では独自ブランド「スーパーゼロ」などを展開し、売上高23億円を達成しています。
「繊維産業に明日はない、跡をつぐなと父親に言われて育ちました。福島大学の教育学部に行き、教員をした後、自ら父親に家業を継ぎたいと言いました」
2000年代、中国から安い製品が入ってきたことが、売上に大きく影響したと浅野氏は語ります
「機械を購入し環境を整えたのにも関わらず、受注の約束は守られませんでした。下請けって本当に惨めだなと思いました。世界一の機械と技術があるのに、仕事がなくなる現実。『下請けのままではダメだ』と痛感し、自分たちで最終製品を持とう、町工場でもブランドを持とうと決めました」
しかし、その道のりは決して平坦ではありませんでした。福島県の双葉町に新工場を建設するため30億円を投資し、復興に貢献しようとした矢先にコロナ禍が襲いました。さらに浅野氏自身も病に倒れたのです。
「昨年、病に倒れた時は、会社がどうなるかと不安に思う社員もいたと思います。でも誰ひとり辞めませんでした」
その後、浅野氏は100億企業を目指すことを決意します。
「幹部社員に飲みながら『100億企業を目指す』という話をしたら、涙ぐみながら賛同してくれました。息子にも『俺は本気でやる、ついてきてくれるか』と言ったら、『親父、楽になった。方向が見えるのは楽だ』と言ってくれたのです」
また、若手社員を温泉に連れて行き、「100億企業になったら何がしたいか」と一人ひとりに語らせたといいます。
「みんなが夢を語り、やる気をみなぎらせてくれました。福島県の社員は、浅野撚糸が100億になったら福島は確実に復興するよね」と言ってくれました。
「20億の売上の中で利益を出していくのと、100億を目指すのでは日々の行動、投資の方向、全てが違ってきます。とにかくアドレナリンが出ます」
浅野氏は、100億円を目指す「大義」として、3つの目標を掲げました。
「1つ目は、社員の給料を上げること。2つ目は、日本の繊維産業、そして町工場が勇気を持てるようになること。3つ目は、福島の復興に貢献することです」
司会からの「金融機関はどんな反応でしたか?」との質問に対し「『最初は怒られましたよ。またカネを使うつもりか!』と。『いやいや、気持ちの問題ですよ』と説明したところ、金融機関は、良いことだ、応援するよ、と分かってくれました。100億宣言をすると、もう逃げられませんから・・・。」
宣言することで、社員、取引先、金融機関に対する説得力が違うようです。浅野氏は、実に淡々と語るのです。穏やかに、時に小さく微笑みながらも、しかし聞いている人々にとてつもない力強さ、芯のあるエネルギーを感じさせるものでした。聴衆の多くは、その静かな闘志に圧倒され、固唾をのんで耳を傾けていました。
山崎寿樹氏(株式会社ONDOホールディングス)──「地域を沸かす」28歳の起業家

山崎氏は、登壇した3人の中で最も若い経営者です。28歳で温浴施設を再生したことをきっかけに起業し、現在は温泉、サウナ、宿泊、さらにはプロ野球独立リーグやサバの陸上養殖まで手がけるコングロマリットを築き上げました。グループ全体の売上高は30億円。100億企業をまっすぐに見据えて進んでいます。
「当社の特徴は、人材にフォーカスした経営です。設備産業と言われますが、私たちは個性のあるメンバーを中心に運営をしています」
山崎氏のビジョンは「地域を沸かす」。お風呂屋さんだからこその言葉遊びですが、その実態は極めて真剣です。
「箱物で起業する人は少ないと思いますが、温浴施設の再生をきっかけに起業しました」
同社のもう一つの特徴は、すべての事業をM&Aや事業譲渡で拡大してきた点にあります。
「プロ野球の独立リーグ“埼玉武蔵ヒートベアーズ”の球団経営をしたり、サバの陸上養殖を手がけたりしています。これらは全てM&A、事業譲渡によって多角化していきました」
さらに山崎氏が重視しているのは、30代のメンバーに子会社の社長を任せ、経営人材を育成することです。
「厳しい意思決定や現場経験を積みながら、ボードメンバーを育成しています」
若さは時に経営者としてはマイナス要因にもなり得るし、時にパワフルな武器にもなるもの。山崎氏からは、ロジカルな思考とともに「沸騰する熱」を持って、後継者を育てながら、自身も大きく成長している様子が伝わってきました。
「工場が汚い会社が最高」──M&A実践者が明かすリアルなノウハウ
100億円を目指す企業にとって、M&Aは重要な選択肢の一つです。しかし、多くの経営者は躊躇します。実際にM&Aで成長してきた経営者たちは、何を見て、どう判断しているのでしょうか。
M&Aで重視する「2つのパターン」
M&Aで企業を買収する際、何を一番重視しているのか。この問いに対する山崎氏の回答は、意外にもシンプルでした。 「同じお客さまに違うものを売るか、同じものを違うお客さまに売るか。この2つのパターンでないと難しいと定義しています」 最初に入った会社でデューデリジェンスを担当し、数多くの企業を見てきた経験もある山崎氏。しかし、実際に自分が経営する立場になって気づいたことがあったそうです。 「知っていることと、できることは実際に違います」 この気づきが、M&A戦略の原則を生み出しました。 埼玉県を中心に温浴施設を展開し、すでに地域で認知度もあり、BtoCビジネスで顧客基盤も確立している。そこで埼玉県内であれば異業種でも展開可能という判断になりました。野球事業、独自産業系のパン屋、温泉サバ陸上養殖場など、一見ばらばらに見える事業展開も、実は「同じお客さまに違うものを売る」パターンなのです。
一方、三重県で展開するエリアカンパニーは、同社が得意とする温浴施設を「違うお客さまに提供する」パターン。慣れている事業で新しい地域のお客さまにアプローチする戦略です。 「事業の見立てはこの2つのパターン。そのうえで、実際に買収する企業やグループインさせる事業の将来性をしっかり見ていくことを大切にしています」
前田氏のM&A視点──「工場が汚い会社には改善余地がある」
前田氏のM&Aの視点は、ユニークです。
「汚い工場の会社が好きです」
会場がどよめきました。「汚い工場!?」多くの人が首をかしげる中で、「色々なことができそうで、わくわくする」と前田氏は続けます。
「環境を整備し、しっかり設備投資をすることで、社員のエンゲージメントが上がります。トイレや休憩室を綺麗にすることも重要です。汚い工場の方が改善余地もたくさんあって、やりがいがあります」
汚い、だから「整えて働きやすい環境にして、ここでがんばりたいと思えるようにきれいにする」それが従業員のモチベーションに結びつくのだと前田氏は語りました。
前田氏の「シンプルPMI」──M&Aの8割は買収後の統合
前田氏は、世の中ではM&Aをするときが注目されますが、大事なのはその後のPMI(買収後統合)だと断言します。同社が実践している「シンプルPMI」は、3つの柱からなります。
①数字(真実)を見せる
「月次決算で、PLとBSを全社員に見せます。数字をはっきりさせることで、透明性が生まれ、当事者意識が高まります」
②文化の原点に立ち返る
「創業の理由は社員にとって絶大な納得力があります」
前田氏は、BBSの例を挙げました。BBSは元々、BMWなどの高級車に純正採用される世界的なホイールメーカーとして知られていましたが、買収時は経営が厳しい状況でした。
「創業者の思いは『ホイール技術はモータースポーツから』でした。その原点に立ち返り、4年前にF1の統一ホイールとして採用されることに成功しました。創業者の思いをしっかり伝えることで、社員のモチベーションが上がりました」
③ジョブチャレンジ制度とワンファクトリー制度
「ジョブチャレンジ制度は、社内で自由に転職できる制度です。これにより、人材の流動性が高まり、適材適所が実現します」
「ワンファクトリー制度は、忙しい工場をみんなで助ける仕組みです。全工場の稼働率を見て、稼働率が低いところはすぐに忙しい工場の手伝いに入ってもらいます。これで工場の閑散期をなるべく無くしています」
社員の可能性を自由に試せる制度を整えることでエンゲージメントも効率化も向上させ、今いる人員を最大限に活かす、こうした改革が100億企業への一歩となるのでしょう。
山崎氏のホールディングス経営
山崎氏は、ホールディングス化後の経営管理について語りました。
「月次決算は必ずやって、月に1〜2回は各子会社の社長とミーティングをします。数字を見ながら、改善点を話し合います」
そして、数字だけでなく、現場の空気感も大事にしています。
トップが常に「現場」を意識し、常に「現場の現実」を確認することが、次の一手を決める大切なポイントなのです。
また、地域企業の現場から「地域の観光施設が外国企業に買収されている。知的財産やブランドを適切に評価する仕組みが必要」という問題意識の投げかけがありました。
優秀な人材をどう確保するか──ユニークな採用戦略
浅野氏の「顧問10人契約」戦略
浅野氏は、外部人材の登用について失敗談から語り始めました。
「過去に紡績の経験豊富なトップ人材を採用したのですが、命令口調が強く、下請けさんや、社員と合わずに退職してもらうことになりました」
この失敗から、浅野氏は独自の方法を編み出しました。
「現在は約10人と顧問契約をしています。一緒に働きながら、本当に相性が合うかを見極めます。お互いに納得したら正式に採用するという形です」
さらに浅野氏は、採用力の向上にも手応えを感じています。
「かつては、高卒新卒の採用が難しかったのですが、今では見学希望者が増えています。オープン・ファクトリーとすることで『こういう企業だったのか』『こんなブランドを展開しているのか』と知ってもらうことで、若い世代に関心をもってもらえるようになりました。企業の知名度とブランド力が採用力につながっています」
地方の中小企業にとって、地元の若者の採用は重要であり、それは逆に言えば大都市に流出するかもしれない希少な人材を地元に確保する重要な課題でもあります。
浅野氏の人材育成で特筆すべきは、毎月の経営会議です。
「毎月、経営会議をやっています。19歳の若手から63歳のパート社員まで、全員が発表します。最初は『ゴッコ』ですよ。4時間かかりますが、これによって全員が当事者意識を持ちます。希望する銀行さんにも丸裸の状態を見てもらっています」
100億円を目指す中で直面する、ファイナンスの課題
技術の積み重ねの先にしか、ドローンやロボットは創れない
会場から飛び入りで参加した株式会社カネバン金子氏の登場は、会場を大きく沸かせました。株式会社カネバンは、東京青梅市に本社を置き、塗装・印刷技術を活かしてキャラクターグッズやバイオマス製品を製造するベンチャー企業です。笑顔で舞台へと向かった金子氏は、おおらかな表情ながら、切実な課題を提起しました。

金子氏は現在、地方の技術を持つ企業を狙い撃ちでM&Aを進めています。規模がそう大きくない企業には、PMI(買収後の統合プロセス)といった話をしても、なかなか通じません。だからこそ金子氏は、浪花節で「一緒に100億をめざそう!からの月次決算」と酒を飲みながら熱く語り合い、相手の心をつかむ。そしてグループイン後はしっかり管理していく、そんなスタイルで成長を加速させています。
「私の会社は売上19億円で、今期30億円をめざしています。そして2〜3年で100億円を達成したい。しかし、施策や金融機関の理解が追いつきません。ファイナンスが最大の課題です」
特に、10億から50億にかけてのファイナンスの壁は深刻だと金子氏は訴えます。たとえば、プレス加工の企業をM&Aをしようとした際、金融機関からは「そうは言っても社長にプレス事業の経験はないでしょう」と指摘されたそうです。
「すぐに『コングロマリット・ディスカウント*』だと言われます。でも、こうした技術を積み上げた先にしか、ドローンやロボットは創れない。それを潰す風潮はおかしいと思っています」
*コングロマリット・ディスカウント:複数の異なる事業を抱える複合企業の企業価値が、個別事業の価値の合計より低く評価されてしまう現象
金子氏の言葉には強い信念が込められていました。そして、こう宣言したのです。「2〜3年で真っ先に100億を卒業します」
金子氏がこの場で急遽登壇したのは、こうした熱い想いや苦しめられている課題があることを皆さまと共有したかったこと、そして「皆さまとともに熱い気持ちで」前進していくためでした。金子氏の発言に、会場の多くの参加者が共感し、勇気づけられたのではないでしょうか。
経営者が100億を目指すという目標に向かって、政府・自治体も金融機関も支援機関も一体となって向かっていこうとする情熱が感じられた瞬間でした。
銀行との向き合い方──「数字で語れること」、「パーパスで惚れさせること」、そして「オープンであること」
パネルディスカッションのクライマックスは、成長資金を調達する上での金融機関との関係についての議論でした。
日本政策投資銀行の常務である増田氏は、金融機関の立場からこう語りました。
「金融機関は預金者のお金を預かっています。そのお金で企業を支援するため、判断は論理的でなければなりません」
一方で、経営者側がやるべきことも明確に指摘します。
「細かいレベルまで数字を把握することが大事です。部門別の収支など、見える化が必要です。これが成長資金を得るための第一歩です」
「さらに、パーパス、大義や夢、何を実現したいかというストーリーも重要です。金融機関の人も、つまりは"人"です。数字がしっかりした上で、『あなたの情熱に惚れ込みました』と言われるような、パーパスや物語を持つことが大事です」。さらに、浅野氏の発言に触れつつ、「金融機関に対してオープンであることも大事です」と指摘しました。つまり、「数字で語れること」「パーパスを持つこと」「オープンであること」で少しでも成長資金の調達がしやすくなるという点を述べました。

増田氏は、金融機関側の課題にも言及しました。
「見た目の決算数字が悪くても、実態が良い会社はたくさんあります。」
一方、金融機関では「わからないからノー」ということがまかり通るのも事実。
そのうえで、経営者側にこう助言しました。「経営者の皆さまが金融機関をエデュケートして頂くことや、自社の業界に強い金融機関を探すことも大切です。」
金融機関にも得意・不得意分野があります。製造業に強い、観光業に強い、M&Aの経験の有無など、地域や経営方針によって「注力しやすい」分野が異なるのも事実です。透明感をもって金融機関と接し、「長いお付き合い」をしていくこともお互いを理解する上で重要です。
最後に、増田氏はこう強調しました。
「今100億宣言で経営者側に火が付いた、これを金融機関側が止めることがあってはなりません」
これを踏まえて中小企業庁より「今、一気に変える必要があるから補助金までやっているが、本来はファイナンスの役割が重要。成長資金が調達できるよう経営者側で意識すべきこと、金融機関側で対応すべきこと、両面を進めて行く必要があり、本腰を入れていきたい」との発言がありました。
志を共にする仲間たちと共に
予定の時間を延長して続けられたパネルディスカッションは、具体的で、時に生々しく、そして何より熱量に満ちたものでした。
第1部の締めくくりに、主催者を代表して中小機構の茂木副理事長から「中小企業が持つ技術力、創造力、そして“挑戦する力”はかけがえのない資産。中小機構は伴走者として支援を全力で行っていく」として、改めて意気込みが語られました。
その後の第2部「経営者ネットワーク及び交流会」では、約100名の経営者が売上規模ごとにテーブルに分かれ、グループディスカッションが行われました。多くの皆さまの関心はM&A、人材確保、成長資金の調達です。これらを実際に「成し遂げた」経営者に質問が集中していました。時に笑い声が、時には議論が白熱し、たとえ異業種であろうと、それぞれの思いとともに共通の悩みや今後の道筋について、熱心に語り合う姿があちこちで見受けられました。
「100億宣言」は、まだ始まったばかりです。しかし、この日集まった経営者の皆さまの熱気、具体的な実践論、志を共にする仲間との出会い、そして皆さまが各地で起こす「変化」は、やがて大きな「うねり」となり、地域から日本経済を変えていく原動力となっていくことでしょう。

